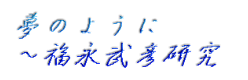 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
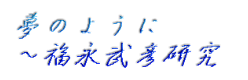 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
| 〜福永武彦と黒田三郎と萩尾望都(b)〜 |
| 考えていたことは「この小説に全体を突き抜けるようなテーマがないだろうか」ということだった。この小説は福永自身の −−あれで主人公(忘却の河)が救われるとはもちろん思わない、けれども、救われる方向へ、せめて、向けておきたいですね(國文學S.47.11月号 菅野昭正との対談 「小説の発想と定着」のちにS.56.1 講談社 福永武彦対談集 「小説の愉しみ」に収められた) という述懐がありながらも、その「救い」は、かなり解りにくいものになっている。主人公である藤代は最後には娘の美佐子からの家族としての情愛を得られるが、これを救いだとするのに納得しない人もいる。「藤代家」のことが書いてあるので、家族がテーマであり、三木だけが仲間はずれのように見えるが、それにも大した意味があるとは思えない。この小説に「救い」に関して何か全体を突き抜けるようなテーマがないものだろうか、と考えているところに、私は黒田三郎のこの詩に出会ったのだ。 この詩は『ひとりの女に』という詩集の中の一つであり、その詩集については三木卓の次の文章によく言い表されている。 −−『ひとりの女に』は、戦後の荒廃とした現実を何一つ所有しないで生きていた青年の 愛との出会いが中心テーマになっている詩集です。(中略)失うべきものはすべて失ってしまったと思っている、生への確信の揺らいでいる一人の青年の姿がまず浮び上ってきます。そして、そういうデスペレートな心情におちこんでいた青年こそ、一人の女の愛のすばらしさをよく知ることができたのだ、ということがわかります。(「黒田三郎論」思潮社現代詩文庫『黒田三郎詩集』所収) 私は、この文章を読むまでもなく、この詩を理解した。それは『トーマの心臓』の先のフレーズに続く、こんな言葉のせいだったかも知れない。 愛していると いった その時から 彼はいっさいを 許していたのだと 彼がぼくの罪を 知っていたかいなかが 問題ではなく −−ただ いっさいを なにがあろうと 許していたの だと (小学館文庫『トーマの心臓』448頁) そして私は思ったのだ。一人の者の愛により救われるということが、『忘却の河』にも書かれているはずだと。ただし、本当に救われるかどうか、どのように救われるかは、作中人物によってそれぞれ異なっているかも知れない。 そこで改めて『忘却の河』を読み直すと、その「救い」は既に1章で準備されていることが解る。1章で藤代が石を投げたのは、救いをあきらめたのではなく、「罪」や「惨めな生」から自由になったからだと思える。ただ、1章だけではそれが解りにくい。このテーマによる救いが明言されるのは4章でゆきが「愛というものはそのひとのために死ぬことができる場合にもっとも強くもっとも烈しい」と思う箇所である。香代子は、こうした母親の想いを知り、愛のない下山を拒む。けれど、こうしたことを表現する箇所は思っていたより少ない。これは、どういうことだろうか。 喪失感を埋めるものとして愛を書いた黒田三郎の詩と同じように、『忘却の河』でもマイナスの側面である「死(終り)」や「罪(裏切り)」や「忘却(魂の喪失)」で愛を書いてはいないだろうか。5章の三木は結局、喪失感を埋めようとする愛には走らなかった。美佐子は父親への親愛の情を持ったものの、藤代やゆきのような愛に至ったとは言えないだろう。このテーマに一番似つかわしいのは、ゆきであり、藤代である。それに気づいた香代子が続き、美佐子や三木は遠いところにいる。 藤代は「燃え尽き」るほどの恋愛を看護婦である彼女としたわけではないだろう。むしろ「彼女」の方が恋愛に関しては、深いものがあった。「彼女」が恨み言を言う箇所は一カ所もない。藤代には、そうしたことが解っていなかったのだ。忘れようとしていたものを忘れないと決心したときに、彼女の本当の愛を藤代は手に入れたのである。それは最終章で次のように書かれている。 わたしは嬉しいわ、あなたがまだわたしのことを忘れないでいてくれるということ。みんな不幸なのね。みんな可哀想なのね。でもあなたはわたしのことを決して忘れないわね。 僕は決して忘れないよ、と彼は言った。 僕は決して忘れないよ、と私は言った。 (新潮文庫『忘却の河』268頁) by Yuichi Toyokura(H.11.4.18) |