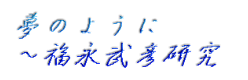 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
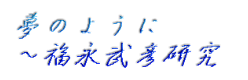 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
| 〜秋の嘆きと失踪事件と初めての児に〜 |
| お前が生まれて間もない日。 禿鷹のように そのひとたちはやってきて 黒い皮鞄のふたをあけたりしめたりした。 生命保険の勧誘員だった。 「ずいぶん お耳が早い」 私が驚いてみせると そのひとたちは笑って答えた。 「匂いが届きますから」 (吉野弘「初めての児に」) 今回も「狂気」の話だ。それで福永の『秋の嘆き』の話である。加田伶太郎全集に所収の『失踪事件』を読んでいて、気になる箇所があった。話の筋は省略するが、それはこんな会話のくだりだ。 「その泊ったお家に少し気の変なお嬢さんがいて、看病してもらっているうちに、学生さんの方も気が変になった、というのはどう?」 「精神病は伝染しないんだ。どうも君はロマンチックでいけない」 これは、狂気の解釈において『秋の嘆き』でロマンチックの粋を究めた福永の言葉とは思えない。けれど、『秋の嘆き』で麻野に言わしめた 「僕は今、何だか気が狂いそうなほどです。僕は一生あなたのことは忘れません。」 という言葉が全くの戯言であろうはずもない。『秋の嘆き』が1954年(福永36歳)、『失踪事件』が1957年(同39歳)なので、かつての自分のロマンチシズムを恥じ入って、そういうことを書いた、というのは簡単すぎるだろう。だから、もう一度「狂気」について考え直してみた。 私は以前に「狂気は既存の概念に収まりきらない何ものか」であると書いた。また、「狂気は世界の外に出て内に働きかけ世界を変えていく」とも。このイメージに近いものは「死」だと思う。これは、多くの人が、うすうす気づいていることだろう。収まりきっているものは「生」であり、内にあるものも「生」である。「死」は外に置かれたまま、普段は意識にのぼらない。「狂気」そのものは、必ずしも人を殺さないだろう。けれど、その「死」との近さから、呼び寄せられることもあるだろう。 まだ幼いころに、自らを死に追いやるということを考えたり、狂しさに憧れたりはしなかっただろうか。こうしたことは、さほど特別ということでなく、なおかつ大人になれば、あたかもそんなことは考えたこともないかのように暮らすようになる。それは何故だろうか。人は「死」に向かって生きている。だんだん「死」に近付いている。私たちは、いま「死」から遠い。何故だろうか。 私たちは、いきなり「死」の遠くに置かれたのだろうか。そして、それぞれの「生」を始めたのだろうか。むしろ「死」の近くから、もっと言えば「死」から「生」を始めたのではないか。「死」の匂いをただよわせて。そして、だんだん遠ざかってきたのではないか。人は育つ。「死」から遠ざかる。そして老いる。「死」に近付いていく。そして「生」の真ん中で、「死」から一番遠い。 幼いころ、私たちは「死」に近かったから、それを考えたのだ。そして「狂気」も近かった。私たちは生きるための知識を与えられるよりも早く、生きるための思考をしなければならなかった。「死」から生まれたばかりの、弱々しい魂で。いつ狂ってもおかしくなかった。一殴りで、あっけなくなりそうな未熟な身体しか持たずに。 そして中には、「死」や「狂気」から、うまく遠ざかれない人たちが居るだろう。親しい大事な人の「死」の匂いのせいで。自らの身体の弱さのせいで。疎外された意識に触れて。置いてきぼりを食らった自らの魂とともに。 1947年、福永、胸部疾患の手術を受けるために上京、清瀬村の東京療養所に入る。1952年、秋、信濃追分に滞在し七年ぶりに堀辰雄に会う。1953年、堀辰雄亡くなる、清瀬村の東京療養所を退所し、学習院大学文学講師となる。1958年、秋から冬にかけて急性胃炎にて国立第一病院に入院。(源高根編「年譜」) 福永は「死」から遠ざかりきってしまうことは、できないでいただろう。けれど幼すぎる狂気の解釈を「ロマンチックでいけない」と言えるくらいには、生きることができたのではないかと信じたい。 by Yuichi Toyokura(H.13.5.28) |