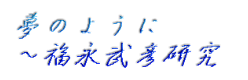 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
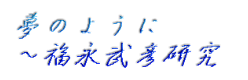 (C)1998
Yuichi Toyokura
(C)1998
Yuichi Toyokura
| 〜空を翔べたら〜 |
| では、これに、名前と、住所と、それから、面会人との関係を記入して下さい。そう言って、受け付け嬢は、埃のかぶったノートと、ボールペンとを差し出した。そしてすぐに、彼の担当の医師を呼びに行った。 私は、まだ一頁目が埋まっていないノートを前にして、関係を「友人」にするか、「親友」にするかで、迷っていた。常識的には、「友人」と書くべきなのだろう。けれど、「父」だとか「息子」だとか、「兄」だとか「弟」だとかが並んでいると、よほど患者と親しい者でなければ、ここに来てはいけないような気がしていた。すると、いつの間にか、医師が私の後ろに立っていて、医師の見ている前で、私は「友人」と書いた。 医師は割合と若く、小奇麗な白衣に身を包み、始終笑顔を絶やさない男だったが、どうも私は好きになれそうになかった。医師は先ず、このような所に来るのは初めてですか、尋ねた。ええ、初めてです。そうですか。ここでの面会は医師の立ち合いの下に行われます。けっして患者を興奮させるような事がないように、言葉遣いには十分注意して下さい。いいですね。そう私に念を押すと、医師は私を「彼の個室」に案内した。 この病院には、普通の病院で経験するような、薬臭さがなかった。エレベーターを降りてまっすぐ歩き、突き当りを右に曲り、さらに廊下を右に折れてすぐの部屋が「彼の個室」だった。これまた愛想のよい看護婦が一緒に付いてきたが、ドアに掛っていた鍵は医師が自分で開けた。医師の後に付いて入った部屋は、意外と暗い感じがした。彼は私を見るなり、やあ、君か、言った。 部屋には高い位置に窓が一つしかなく、昼間だというのに蛍光灯がこうこうと灯っていた。もともと白く塗装された部屋が、よりいっそう白々と輝いて見えた。白い花瓶には枯れる事のない造花が生けられており、その花瓶の傍らに白い表紙で覆われた二冊の本が置いてある。どこからか、生臭い臭いが、微かにする。 やあ、本当に久しぶりだ、彼は言った。私と同い年のはずだが、相当に老け込んでいて、十も年が違うように見える。無精髭のせいかも知れない。彼は暫く、私と医師とを代わる代わる見比べていたが、やがて医師に、出ていって貰えないか、頼んだ。医師は当然のようにして断ったが、彼と私とで頼み込んで、結局、十五分だけならいい、という事になった。 どうせ廊下で聞き耳を立てているよ、そう言いながら彼は、花瓶を置いた台の引き出しの中から生魚を取り出して、私の目の前に掲げた。それ、どうしたんだ。今朝の朝食のおかずだよ。また、どうしてそんなものが引き出しの中にあるんだい。こっそり調理場に行ってね、どうせ食べないから調理しないのをくれないかと頼んで、貰ってきたんだ。それで、それをどうしようというんだい。すると彼は、今度は引き出しの中から得体の知れない電気器具を取り出して、言った。これを使って、電流を流すんだ。それで、私が尋ねると、そうしたら、言って彼は少しためらったようだったが、大きく息を吸って言葉を繋いだ。そうしたら、こいつが空を翔ぶんだ。 それから彼は、「魚が空を翔ぶ理論」というのをとうとうと講釈し始めた。その中で使っている用語というのが、私には意味の判らないものばかりだった。しかしながらも、魚には本当は空を翔ぼうとする本能があるのだが眠っている状態にあり、その本能を目覚めさせれば魚は空を翔ぶ事が出来るんだ、というような粗筋だけは掴めた。 でもこの魚には翼がないじゃないか、私が問うと、翼が在るか無いかなんで問題じゃないんだよ、彼は応えた。どんなに完全な翼が在ったとしても、翔ぼうとしなければやはり翔ぶことは出来ないからね。 だってこの魚は死んでいるんだよ、私は少しむきになって言うと、彼は少し悲しそうな顔をして言った。そう確かに今は死んでいるかも知れない。でも、この魚が翔ぼうとした時には、その魚は生きているという事なんだよ。私は、黙ってしまっていた。 それを、あいつらは、僕の理論は事実を無視していると、ちっとも科学的ではないと言うんだ。僕の理論は虚しい羽ばたきだと言って、笑うんだよ。私は、黙っていた。 この魚は、この形のままで翔べるんだ。科学は、新しい事実だってつくるんだよ。愉快じゃないか。ねえ、君もそう思うだろう。私は、黙っていた。彼も黙ってしまった。そして彼は、部屋に一つしかない窓の外に目を遣ると、雲一つ無い空の青を食い入るように見詰めた。 僕は。ようやく彼が口を開いたので、私は顔を上げて彼を見た。僕は、時々、自分でも、自分の事を狂(おか)しいと思うよ。私は、黙っていた。 でも僕には、自分が、どういうことをすれば、人から狂しいと言われるのか、どういうことをしていれば、人から狂しいと言われないで済むのか、判らないんだよ。ねえ、君。みんなは、そういうことが判っていて、僕のことを馬鹿にしたり、笑ったりするんだろうか。私は、黙っていた。 ねえ、君。君も判っているのかい。私は、黙っていた。彼は、涙ぐんだ。僕だけが。僕だけが、判らないんだっ。とつぜん彼は、大声で泣き始めた。私は、黙っていた。医師が、部屋に飛び込んできた。 医師は、私を少し睨んだが、すぐに患者を落ち着かせに取り掛かった。私は、そのままそっと病室を抜け出し、受け付けの前まで戻ってきた。ノートとボールペンが、そのままに置いてあった。私は、「友人」の二文字を塗りつぶした。 病院の外に出ると、辺りはもう暮れ掛かっていた。このまま疎らな病院の駐車場を横切れば、駅にたどり着く。病院の前から右手に伸びる細いじゃり道は、小さな林の向うに消え入り、行方も知らない。 誰もいないホームで、時刻も確かめずに、ただ電車を待っている。ちち、ちち、ち、と小鳥のさえずる音がするが、姿は見えない。遠くに、高く薄くたなびく雲。明日は、晴れるだろうか。 私は電車に乗り、席は空いていたが座らずに、そのままドアにもたれかかった。つるべ落としの日も落ちようとする秋の日、ふっと日差しが弱くなる。喉から振り絞るようにしたら、あー、やっと声が出た。上を向いた。息を飲んだ。下を向くと、涙が零れた。 by Yuichi Toyokura |